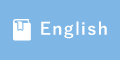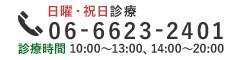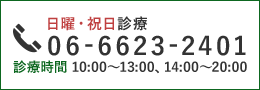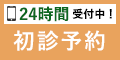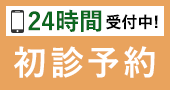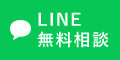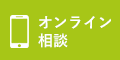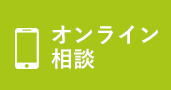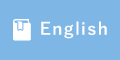先日、当院にて院内勉強会を開催しました。今回お招きしたのは、大阪大学大学院歯学研究科イノベーティブ・デンティストリー推進センター特任教授であり、理事長にとって同窓会やインプラント学会を通じて長年お世話になっている旧知の先生、十河基文先生です。
十河先生は、歯科の研究と臨床をつなぐイノベーションを次々と生み出してこられた第一人者。現在も新しい検査機器の開発に取り組まれており、今回のご講演ではその最先端の内容を直接伺うことができ、スタッフ一同とても貴重な学びの時間となりました。
インプラント治療と歯周病菌の関係
近年、多くの患者さんにとって身近な治療法となったインプラント。その一方で「インプラント周囲炎」という新しい課題が注目されています。
原因はさまざまですが、実はプラークコントロール不足が28.8%を占めるという報告があるそうです。やはり日常のケアが欠かせません。
さらに、歯周病菌の中でも特に悪性度が高い「RED COMPLEX」と呼ばれる菌群があります。これを短時間で検出できるのが、十河先生が開発されたリアルタイムPCR法による新しい検査機器です。
リアルタイムPCR法とは?
PCRとは「ポリメラーゼ連鎖反応(Polymerase Chain Reaction)」の略で、DNAをコピーして増幅する技術です。ほんの少しの遺伝子情報でも、何百万倍にも増やすことで検出できるようになります。
その中でもリアルタイムPCR法は、DNAが増える様子を“リアルタイム”でモニターできる方法です。つまり「菌やウイルスがいるかどうか」だけでなく、「どのくらいの量があるのか」まで数値として把握できます。
例えるなら、
- PCR:懐中電灯で暗闇の中の物を見つける
- リアルタイムPCR:さらにカウンターで「何個あるか」数えてくれる
そんなイメージです。
この方法を使えば、これまで数日〜数週間かかっていた歯周病菌の検査結果が、30分以内にその場でわかるようになりました。
これは新型コロナ検査でも注目された「POCT(臨床現場即時検査)」の考え方そのもので、定期的なメンテナンス時にその場で菌の状態を確認できるのは、患者さんにとっても私たちにとっても大きなメリットです。
ご自宅でもできる口腔機能検査
もう一つ印象的だったのが、口腔機能検査機器の紹介です。
口腔機能検査には、噛む力・飲み込む力・口の動きなどさまざまな項目がありますが、今回ご紹介いただいたのは、口の動きを検査する新しい機器でした。
この機器の特長は、従来のような院内測定にとどまらず、次のような点にあります。
- 測定結果を記録・クラウド管理できる
- ご自宅から検査・データ送信が可能
- ゲーム感覚で訓練にも活用できる
つまり、患者さんが医院に来院しなくても、ご自宅で測定を行い、その結果を共有できる未来が近づいているのです。これは、高齢化社会における「通院負担の軽減」や「継続的な口腔機能管理」にもつながると期待されます。
今回のご講演で強く感じたのは、最新研究がいかに患者さんに還元されていくかということでした。
歯周病菌の管理も、口腔機能のチェックも、従来よりずっと早く・正確に行える時代になってきています。しかも、ICTを利用して、より早く、どこでもできるように工夫されつつあります。
そして何より印象的だったのは、十河先生の製品開発に対する情熱とベンチャー精神でした。「患者さんのために、よりよい歯科医療を」という思いから新しい技術を形にする姿勢は、私たちにとっても大きな刺激です。
私たちも日々の診療や定期検診の中で「どうすればもっと患者さんに良い治療や予防ができるか」を考え続けています。今回の学びを活かし、皆さまのお口の健康を守るためにこれからも努めてまいります。